皆様、こんにちは。 U5swです。
今回は中央快速線と青梅線に関して説明します!
中央快速線と青梅線の概要
中央快速線

- 開業日:1889年4月11日
- 起点駅:東京駅
- 終点駅:高尾駅
- 駅数:24駅
- 路線距離:53.1km
- 路線記号:JC(JCと案内している区間は東京〜大月間)
- 線路数:複線(御茶ノ水〜三鷹間は中央・総武緩行線と線路別複々線)
- 保安装置:ATS-P
- 最高速度:100km/h(八王子〜高尾間の特急列車は130km/h)
- 車両基地:豊田車両センター(武蔵小金井派出所)
東京駅から甲府駅、塩尻駅、中津川駅を経由し名古屋駅に至る「中央本線」のうち、東京駅から高尾駅までの首都圏エリアにおいて、都心区間を中心に通過運転を行う区間を「中央快速線」と呼びます。
東京〜高尾間の運行を中心に、一部列車は立川駅から青梅線、更には拝島駅から五日市線に、高尾駅以西から中央本線の大月駅、更には大月駅から富士急行線の河口湖駅まで乗り入れています。
青梅線

- 開業日:1894年11月19日
- 起点駅:立川駅
- 終点駅:奥多摩駅
- 駅数:25駅
- 路線距離:37.2km
- 路線記号:JC
- 線路数
- 三線(立川〜西立川間、内1線は青梅短絡線)
- 複線(西立川〜東青梅間<東青梅駅手前まで>)
- 単線(東青梅〜奥多摩間<東青梅駅構内含む>※)
- ※東青梅駅のホーム有効長の延長により、東青梅駅は単式ホーム化
- 保安装置:ATS-P
- 最高速度:85km/h
- 車両基地:豊田車両センター
立川駅から拝島駅、青梅駅、御嶽駅を経由して奥多摩駅へ至る路線です。青梅駅を境に需要が大きく変わるため、基本的に立川〜青梅間と青梅〜奥多摩間で運行形態が分かれています。青梅〜奥多摩間は「東京アドベンチャーライン」という愛称が付けられています。
一部列車は立川駅から中央快速線に乗り入れて東京駅まで、拝島駅から五日市線に乗り入れて武蔵五日市駅まで乗り入れる列車があります。
中央快速線と青梅線で運行されている種別
2024年現在、両路線で運行されている種別は以下の通りです。便宜上、特急列車と快速列車、普通列車に分けて説明します。
特急列車
主に6つの列車愛称が運行されています。詳細は以下の通り。
- あずさ号(東京、千葉、新宿〜松本、南小谷間)
- かいじ号(東京、新宿〜甲府、竜王間)
- 富士回遊号(新宿〜河口湖間<新宿〜大月間はあずさ号orかいじ号と併結運転(臨時列車除く)>)
- はちおうじ号(東京、新宿〜八王子間<平日のみ運行>)
- おうめ号(東京、新宿〜青梅間<平日のみ運行>)
- 成田エクスプレス号(成田空港〜八王子間<中央快速線は新宿〜八王子間のみ運行、1日2往復のみ運行>※2024年3月改正で中央快速線での運行は終了、全て新宿発着へ)
特急列車の中央快速線、および青梅線内での停車駅は以下の通り。
- あずさ号、かいじ号、富士回遊号、はちおうじ号→東京、新宿、立川、八王子
- おうめ号→東京、新宿、立川、拝島、河辺、青梅
- 成田エクスプレス号→新宿、吉祥寺、三鷹、国分寺、立川、八王子
快速列車
2022年現在、中央快速線、青梅線の快速列車は6種類あります。詳細は以下の通り。
- 快速
- 通勤快速
- 中央特快
- 青梅特快
- 通勤特快
- ホリデー快速おくたま号(2023年3月改正まではあきがわ号も運行されていたが、廃止)
快速

- 営業区間:東京〜大月〜河口湖、青梅〜奥多摩間
- 運行時間帯
- 全日全時間帯運転(東京〜高尾、青梅間)
- 全日朝夕時間帯運転(高尾〜大月間)
- 平日朝夕時間帯運転(大月〜河口湖間)
中央快速線のベースとなる種別です。東京〜中野間で快速運転を行い、中野以西は平日と土休日で停車駅が異なり、吉祥寺以西は全列車各駅に停車します。
2022年改正以前は、拝島駅から八高線や五日市線にも乗り入れていました。また、2023年3月の改正で朝時間帯青梅線の奥多摩始発東京行きの快速が運行されていましたが、青梅〜奥多摩間のワンマン運転化に伴い廃止されました。
停車駅は以下の通り。
- <平日>:東京、神田、御茶ノ水、四ツ谷、新宿、中野、中野以西各駅
- <土休日>:東京、神田、御茶ノ水、四ツ谷、新宿、中野、荻窪、吉祥寺、吉祥寺以西各駅
平日は中野〜吉祥寺間にある高円寺駅、阿佐ヶ谷駅、西荻窪駅の3駅にも全ての快速が停車します。一方で、土休日は全ての快速が通過し、この3駅に向かう際は、中央・総武緩行線の各駅停車を利用する必要があります。また、土休日の3駅に関しては、快速線のホームにすら立ち入ることができません。
日中時間帯は平日に毎時9本、土休日に毎時8本運行されています。大半の快速は終点まで先着せず、三鷹駅や国分寺駅、立川駅で通勤快速や中央特快、青梅特快、通勤特快、特急を待避しています。
平日と土休日で停車駅が異なる「杉並3駅」問題について
これらの3駅に関しては、東京都杉並区にあることから「杉並3駅」と呼ばれており、国鉄時代からこの3駅に関しては停車、通過の問題で度々問題に上がっています。
緩行線が並行して走っていること、この3駅を通過する通勤快速や特別快速、特急列車が詰まってしまい、スピードアップの妨げになっていることから、通過を要望する方もいれば、この3駅から新宿、東京方面へ通勤通学する方への速達性を確保する意味で、沿線住民を中心に停車を要望する方もおり、この問題は今でも長く並行線を辿っています。
中央線の御茶ノ水〜三鷹間は、御茶ノ水駅を除き全てが系統別複々線(中央快速線と緩行線で別々の複線)となっており、御茶ノ水駅や山手線と京浜東北線の田端〜田町間のように方向別の複々線ではないというのが、この問題の原因と考えられます。線路建設のタイミングが合わなかったため致し方なかったですが、もし中野〜吉祥寺間に限り方向別複々線であれば、杉並3駅の問題は多少改善できると思います。
日中時間帯に京浜東北線が田端〜田町間で快速運転できているのも、同区間で山手線と方向別複々線をなしているからだと思うので、中央線内もこうであればと思うところはあります。
個人的に、平日の早朝、深夜時間帯や日中時間帯の利用者が少ない時間帯も、快速は杉並3駅を通過させて、利用者の多いラッシュ時間帯は停車させる(種別を区間快速にして区別できるようにする)方がいいのでは?と思っています。
通勤快速
- 営業区間:東京→大月→河口湖、青梅間
- 運行時間帯
- 平日夕方時間帯運転(東京発のみ運転)
平日の夕方ラッシュ時間帯に、中央特快や青梅特快に代わって運行される速達種別です。下り(高尾、青梅方面)行きのみの運行であり、上り(東京方面)行きは運行されません。
また、2022年改正前は、拝島駅から八高線、五日市線に直通する列車もありましたが、現在は運行されていません。


五日市線直通の武蔵五日市行きの通勤快速。
停車駅は以下の通り。
東京、神田、御茶ノ水、四ツ谷、新宿、中野、荻窪、吉祥寺、三鷹、国分寺、立川、立川以西各駅
東京〜三鷹間は土休日快速、三鷹〜立川間は特別快速と同じ停車駅となっています。都心から特別快速の停車しない荻窪駅と吉祥寺駅へのアクセスを確保しつつ、国分寺駅、立川駅と立川駅以西への速達性を担っています。
平日夕夜間帯に毎時4本運行されており、三鷹駅、国分寺駅で快速(各駅停車)と緩急接続を行い、通勤快速が通過する駅へのアクセスも確保している他、立川駅で高尾方面or青梅方面へ接続する列車もあります。
中央特快

- 営業区間:東京〜大月〜河口湖間
- 運行時間帯(東京〜高尾、大月間)
- 平日上り:朝ラッシュ時以外運転
- 平日下り:朝夕ラッシュ時以外運転
- 土休日上り:ほぼ終日運転
- 土休日下り:ほぼ終日運転
- <大月〜河口湖間>土休日の朝夜のみ運転
東京〜高尾間を中心に速達運転を行う主力種別です。日中時間帯を中心に毎時3~4本運行されています。一部は大月駅まで直通する他、土休日の一部列車は富士急行線に乗り入れて河口湖駅まで運行されます。停車駅は以下の通り。
東京、神田、御茶ノ水、四ツ谷、新宿、中野、三鷹、国分寺、立川、立川以西中央線内各駅
中野〜立川間は快速(各駅停車)と緩急接続が行える駅の停車に留まっています。東京メトロ丸の内線との接続駅である荻窪駅、京王井の頭線との接続駅である吉祥寺駅も通過し、都心と多摩地区の速達運転に特化しています。一方、立川駅以西は青梅線が分岐したり、快速の本数が減少することから、それらを補うため各駅に停車しています。
運行本数は日中時間帯において、平日は毎時3本、土休日は毎時4本運行されています。
基本的に三鷹駅、国分寺駅で快速(各駅停車)で緩急接続を行う他、立川駅で青梅発着or立川発着の快速(各駅停車)と接続を行うこともあります。東京〜高尾間は全駅先着ですが、高尾駅以西に直通する列車は高尾〜大月間で特急の待避を行います。
2024年3月のダイヤ改正より、日中時間帯の中央特快の内、毎時1~2本が高尾以西でも運行し、大月までの直通運転を行うことを発表しました。これまでは、日中時間帯の高尾以西の運行が211系の普通列車でほぼ統一されていましたが、この改正から高尾〜大月間はE233系に統一されることとなります。
青梅特快

- 営業区間:東京〜青梅間
- 運行時間帯
- 平日上り:早朝に1本、日中時間帯、夕方に1本運転
- 平日下り:日中時間帯に運転
- 土休日上り:朝、日中時間帯に運転
- 土休日下り:朝、日中時間帯に運転
東京〜青梅間で中央線内で速達運転を行う種別です。中央特快とは異なり本数が少なく、平日は日中時間帯に毎時1本、土休日は日中時間帯に毎時2本運行されており、中央特快の補完的役割を担っています。
ちなみに、2022年改正前は、土休日に八高線に乗り入れる青梅特快が運行されていましたが、現在は廃止されています。
停車駅は以下の通り。
東京、神田、御茶ノ水、四ツ谷、新宿、中野、三鷹、国分寺、立川、立川以西青梅線内各駅
東京〜立川間の停車駅は中央特快と同様の停車駅であり、立川以西は各駅に停車し、快速(各駅停車)を補完しています。特別快速と一括りにしない理由としては、
- 昔、国分寺駅に中央特快が停車し、青梅特快が通過する時代があった
- 過去に新宿始発の中央特快に限り、中野駅を通過する列車があった
という経緯があります。速達種別であり、八王子、高尾方面に行くのが「中央特快」、拝島、青梅方面に行くのが「青梅特快」と区別がしやすいので、わざわざ一括りにする必要はないでしょう。
運行本数は日中時間帯において、平日は毎時1本、土休日は毎時2本運行されています。
基本的に三鷹駅、国分寺駅で快速(各駅停車)で緩急接続を行う他、立川駅で八王子、高尾方面発着の快速(各駅停車)と接続を行うこともあります。東京〜青梅間は全駅先着です。
通勤特快
- 営業区間:東京←大月、青梅間
- 運行時間帯
- 平日朝ラッシュ時間帯運転(東京行きのみ運転)
朝ラッシュ時間帯に国分寺以西の主要駅から都心へ向かう方への速達種別です。2024年改正時点では大月駅始発が1本、高尾駅始発が1本、青梅駅始発が2本の計4本が運行されています。停車駅は以下の通り。
- <大月、高尾発>:大月→高尾間各駅、八王子、立川、国分寺、新宿、四ツ谷、御茶ノ水、神田、東京
- <青梅発>:青梅→立川間各駅、国分寺、新宿、四ツ谷、御茶ノ水、神田、東京
特別快速系統が停車する三鷹駅と中野駅すら通過し、国分寺→新宿間をノンストップで結びます。加えて大月駅or高尾駅始発は西八王子駅、豊田駅、日野駅も通過し、高尾駅、八王子駅からの速達輸送も兼ねています。
ただし、朝ラッシュ時間帯の運行により、運行本数がとても多く、快速が2分間隔で運行する超過密運転を行なっているため、スピードは全く出せません。途中立川駅や国立駅、国分寺駅、三鷹駅、中野駅で快速を追い抜きますが、追い抜いた先にすぐ先行の快速に追いついてしまうので、通勤特快は速達性重視というよりは、「国分寺駅以西の駅から都心へ向かう方への遠近分離」を重視した種別となっています。
ちなみに、国分寺→新宿間の所要時間は、日中時間帯の中央特快や青梅特快よりも時間がかかります。また、30分近くドアが閉まらない状態で低速運転を行うことから、国分寺駅停車前には「体調のすぐれない方は快速をご利用ください」という車掌のアナウンスが行われるのが特徴です。
ホリデー快速おくたま・あきがわ

- 営業区間:東京、新宿〜奥多摩、武蔵五日市間
- 運行時間帯
- 土休日朝(新宿発奥多摩・武蔵五日市行き)
- 土休日夕方(奥多摩・武蔵五日市発東京行き)
土休日に都心から奥多摩、武蔵五日市方面へのお出かけ、レジャー等の需要に応える特別快速の1つです。奥多摩発着が「おくたま号」、武蔵五日市発着が「あきがわ号」として運行され、東京、新宿〜拝島間は2列車を併結して運行する「多層建て列車」となっています。E233系0番台のH編成(6+4両の分割編成)が専属で使用され、6両側が「おくたま号」、4両側が「あきがわ号」となります。ホリデー快速ですが、全区間で乗車券のみで乗車可能です。


なお、2022年改正において、中央快速線から五日市線に直通する列車は、「あきがわ号」のみとなっています。
停車駅は以下の通り。
- <おくたま号>:東京、神田、御茶ノ水、四ツ谷、新宿、中野、三鷹、国分寺、立川、西立川、拝島、福生、(※河辺)、青梅、御嶽、奥多摩
- <あきがわ号>:東京、神田、御茶ノ水、四ツ谷、新宿、中野、三鷹、国分寺、立川、西立川、拝島、拝島〜武蔵五日市間各駅
※特定日に臨時停車する場合がある。
中央線内は中央特快および青梅特快と同じ停車駅となっていますが、ホリデー快速の特徴は青梅線内にも通過運転を行うことがポイントです。奥多摩、武蔵五日市方面へのアクセスが中心となっているため、停車駅を絞っています。
2023年改正以降のホリデー快速の運行形態
2023年3月の改正において、ホリデー快速おくたま号とあきがわ号に関しては、今後運行されるグリーン車の導入の準備に伴い、明暗が分かれる結果となりました。おくたま号とあきがわ号の運行状況は以下の通り。
- おくたま号→改正後も運行継続、但し青梅駅にて系統分断が行われ、東京・新宿〜奥多摩間を通しで運行する列車が消滅。加えて青梅〜奥多摩間は臨時列車扱いとなる(基本的に運行する日が多いが)。
- あきがわ号→改正により廃止。
これによって、東京・新宿から奥多摩および武蔵五日市へ直通する列車が完全消滅し、同時に、拝島駅での分割および併合もなくなりました。
現在は東京・新宿〜青梅間のおくたま号が全区間において10両編成で運行しており、青梅〜奥多摩間は6両編成の車両が運行されています。
普通列車
各駅停車と普通列車の2種類があります。詳細は以下の通り。
各駅停車
各駅停車には主に2パターンが存在しており、
- 快速区間が終了し、終点まで各駅に停車する列車
- 中央線の三鷹以西、および、青梅線(五日市線)で完結する列車
この2パターンが存在しています。
快速区間が終了し、終点まで各駅に停車する列車の場合


この列車は当駅で切り離しを行なっていたが、2022年改正で消滅。
下りの快速、通勤快速、中央特快、青梅特快が該当しており、下記の駅から各駅停車として案内しています。
- 平日快速:中野
- 土休日快速:吉祥寺
- 通勤快速、中央快速、青梅特快:立川
駅での列車案内は上記の駅から「各駅停車」と案内します。
また、車両での案内はE233系の場合、種別表示がなくなって行き先のみに、209系の場合は終点まで元の種別のまま(快速)の表示となります。

車内の自動放送は上記の駅から行き先のみの案内となります(209系は自動放送なし)。
中央線の三鷹以西、および、青梅線(五日市線)で完結する列車の場合

全区間「各駅停車」と案内し、駅、車両の案内表示、自動放送は前者と同様です。
ちなみに、2020年3月の改正前には、早朝、深夜を中心に、御茶ノ水〜三鷹間を緩行線経由で全区間各駅停車で走る列車があり、E233系が使用されていました(この時間帯の中央・総武緩行線は、御茶ノ水駅で千葉方面に折り返し運行していた)。しかし、快速線と緩行線の運行を完全に分離する、および快速列車の運行時間帯を拡大するため、この列車は廃止されました。なお、E233系は緩行線経由の列車に限り「各駅停車」と種別表示を行なっていました。
普通
普通列車は主に2パターン存在しており、
- 大宮〜北朝霞〜新小平〜国立〜八王子間を走る「むさしの号」
- 立川〜高尾間に乗り入れ、大月以西へ向かう「普通」
となっています。
大宮〜北朝霞〜新小平〜国立〜八王子間を走る「むさしの号」

大宮〜八王子間を武蔵野線経由で結ぶ直通列車で、2024年改正時点は
- 大宮行きは平日が夕方に2本、土休日が朝に2本、夕方に2本の計4本
- 八王子行きは平日、土休日共に朝に1本、夕方に2本の計3本
運行されています。使用車両は武蔵野線用の209系またはE231系の8両編成で運行されています。
立川〜高尾間に乗り入れ、大月以西へ向かう「普通」


立川〜高尾間に乗り入れる中央本線の普通列車であり、豊田車両センターへの送り込みor返却も兼ねての運用となっています。
車両は中央本線用の211系6両編成で運行されています。
快速列車、普通列車の停車駅まとめ

※マークの内訳: ○→停車、△→上りのみ停車、▽→下りのみ停車、|→通過、||→経由しない駅
定期列車で活躍する車両
最後に定期列車で活躍する車両を簡単に紹介します。
- E353系
- 特急あずさ号、かいじ号、富士回遊号、はちおうじ号、おうめ号で使用される中央線特急(JR東日本)の主力車両。
- E259系<※2024年3月改正で中央快速線での運行を終了>
- 特急成田エクスプレス号の専用車両。朝の成田空港行き、夜の八王子行きの2往復のみの運用に就く。
- E233系0番台
- 快速列車の主力車両、中央線の東京〜大月間、青梅線、五日市線、富士急行線で活躍中、将来的に一部編成にグリーン車導入予定。
- 209系1000番台
- E233系0番台の車内トイレ改造工事に伴う予備車確保を目的に、元々常磐緩行線および東京メトロ千代田線で活躍していた当形式を転属させて運用に入っている。中央線の東京〜高尾間、青梅線の立川〜青梅間(通常は青梅線に入らない)での限定運用で活躍中。E233系のグリーン車導入完了時に撤退する予定。
- E231系0,900番台、209系500番台
- 武蔵野線の主力車両であり、大宮〜八王子間を走る「むさしの号」で使用される。中央線の国立〜八王子間のみで活躍中。
- 211系
- 中央本線の高尾〜塩尻間、および篠ノ井線、信越線の塩尻〜長野間の普通列車の主力車両。ただし、豊田車両センターへの入出庫運用を兼ねて、中央線の立川〜高尾間に普通列車として乗り入れる。




まとめ:種別の豊富さと共に、車両の多彩さもある
いかがでしたでしょうか?
今回は中央快速線と青梅線に関して説明しました。
車両に関しては快速系統はE233系、特急系統はE353系がほとんどですが、一部列車や一部区間ではこれら以外の車両も見ることができます。
また、臨時列車が走る際は今回紹介した車両以外にも出会うことがあるので、とても面白い路線だと思います。
次回は両路線の今後の進化に関して説明していきます。
今回はここまでとなります。最後までご覧くださいましてありがとうございました!

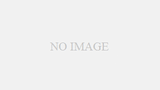
コメント