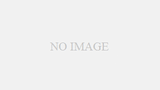皆様、こんにちは。U5swです。
今回は、相鉄線全体の時刻表が発表されたことの中から、パターンダイヤに思ったことを述べていこうと思います。
3月に入り、ようやく全体の時刻表が公開。
先月に2025年3月のダイヤ改正内容が発表された相鉄線。夕方時間帯の特急の増発や土休日夜の新横浜発列車の間隔調整、東横線直通列車の海老名発着本数の増加、日中の湘南台→新横浜間の所要時間短縮といった改正内容が明らかとなり、果たしてどのようなダイヤになるのか色々と予想していました。
そんな中、先日ようやく全体時刻表が発表されたので、その時刻表を見て今回の改正の考察をしていきます。
新ダイヤはこちらのリンクを参照願います↓

パターンダイヤについて
今回注目するのは、日中時間帯のパターンダイヤです。前節でも述べた通り、湘南台→新横浜の所要時間を短縮する関係で、二俣川から先の発着順序が入れ替わることとなります。
そして、相鉄の改正後時刻表が発表される前に、JR東日本の改正後時刻表が発表され、相鉄・JR直通線の列車に関しては、直通先の相鉄線の時刻も掲載されていました。そこで、現行のダイヤと大きく異なるダイヤになっていることが明らかとなりました。更に、相鉄横浜発特急の増発において、横浜発時刻が07分ベースになっていることから、全体的にダイヤパターンが大きく変わることは予想できていました。
そして、公開された後の相鉄線全体の日中パターンダイヤは以下の通りになります。
このパターンダイヤを見た私は、
あれ?改正前より酷くなってね?
という感想を抱きました。
一体どの部分が改正前より酷いと感じるようになったのかを詳しく説明していきます。
①下りの新横浜→羽沢横浜国大間のダイヤホールが更に空いてしまうことに…

まずは下りを見ていくと、相鉄横浜発の優等列車が09分発基準から07分発基準へ、各駅停車が00分発基準から08分基準へ、各々2分ほど前倒して発車するようになりました。これに合わせて、全体的にダイヤの調整を行った結果、本線といずみ野線に関してはほぼ従来通りの列車間隔を保っているため、そこまで問題とは思いませんでした。
しかし、大問題なのが新横浜線、しかも東急直通列車のみが走行するダイヤでは、開業後から悩みの種だった“20分のダイヤホール問題”がずっと解決していないままでしたが、この改正で新横浜発時刻が、
17ー(8分)→25ー(22分)→47ー(8分)→55ー(22分)→…
となり、なんと“ダイヤホールが22分と逆に間隔が広がってしまう”事態になってしまいました…
従来のダイヤより東横線からの直通列車(毎時17,47分発)は1分遅く発車、逆に目黒線からの直通列車(毎時25,55分発)は1分早く発車することとなりました。
東横線からの直通列車(毎時17,47分発)が1分遅く発車することとなった理由としては、東横線の6直系統が遅延に巻き込まれやすいことから、新横浜発時刻を1分だけ遅らせて、遅延の回復を行えるようにしたと考えられます。
目黒線からの直通列車(毎時25,55分発)は1分早く発車することとなった理由としては、相鉄線下りのパターンダイヤが全体的に2分前倒しになったことから、そのバランスを保つが故の調整と考えられます。
このように理由を考えると致し方ない部分が見えてきますが、だからといってダイヤホールを更に広げてしまうのは、利便性の観点からよろしくないことです。
だからこそ、本ブログでは前々から“新横浜〜西谷間のシャトル列車の運行”を提案していますが、今回の改正でも実現に至らず…
勿論、増発は簡単なことではないのは承知ですが、かといってこのまま放置しておくのも良くありません。
どうか、運行できないものですかねえ…
②上りの緩急接続,各方面接続がほぼ崩壊へ…
下りに関しては問題はまだ最小限で済んでいるものの、一方で上りに関しては、もはや問題だらけとしか思えない“ナンジャコリャなパターンダイヤ”となってしまいました。
まずは、本線といずみ野線の分岐駅である二俣川と、本線と新横浜線の分岐駅である西谷の緩急接続,各方面接続についてです。こちらは改正後はほぼ崩壊するダイヤとなりました…
まず、改正前の緩急接続,各方面接続は以下の通り。
- 湘南台発各停横浜行き①←(二俣川)→海老名発快速横浜行き①、海老名発各停西高島平行き
- 湘南台発各停横浜行き②←(二俣川)→海老名発各停JR新宿行き、海老名発特急横浜行き
- 海老名発各停JR新宿行き←(西谷)→海老名発特急横浜行き
- 湘南台発各停川越市or和光市行き←(二俣川)→海老名発快速横浜行き②
- 海老名発快速横浜行き②、湘南台発各停川越市or和光市行きー(西谷)→西谷発各停横浜行き
これが、改正後は以下の通りに変わります。
- 湘南台発各停横浜行き①←(二俣川)→海老名発各停西高島平行き
- 海老名発快速横浜行き①ー(西谷)→西谷発各停横浜行き
- 湘南台発各停横浜行き②←(二俣川)→海老名発各停JR新宿行き、海老名発特急横浜行き
- 海老名発各停JR新宿行き←(西谷)→海老名発特急横浜行き
- 湘南台発各停川越市or和光市行き←(二俣川)→海老名発快速横浜行き②
変更点は以下の通りになります。
- 湘南台発各停横浜行き①が二俣川で海老名発快速横浜行き①で待避せず、一切待ち合わせを行わずに横浜まで逃げ切ること
- 海老名発快速横浜行き①は二俣川での接続がなくなった代わりに、西谷で西谷発各停横浜行きに接続すること
- 海老名発快速横浜行き②、湘南台発各停川越市or和光市行きの、西谷での各停横浜行きの接続が一切ないこと
この変更が何に影響されるのかと言うと、
本線の希望が丘以西の各駅、およびいずみ野線の南万騎が原以西の各駅から、西谷〜横浜間の各停停車駅へのアクセスがしづらくなる
ことが挙げられます。
従来のダイヤだと、海老名方面からは、
- 快速横浜行き①、各停西高島平行きー(二俣川)→各停横浜行き①
- 各停JR新宿行き、特急横浜行きー(二俣川)→各停横浜行き②
- 快速横浜行き②ー(西谷)→各停横浜行き<西谷始発>
湘南台方面からは、
- 各停横浜行き①
- 各停横浜行き②
- 各停川越市or和光市行きー(西谷)→各停横浜行き<西谷始発>
と乗継をナシor1回行うことで、最長でも10分に1本のペースで辿り着くことが可能でした。
しかし改正後は、海老名方面からは、
- 各停西高島平行きー(二俣川)→各停横浜行き①
- 快速横浜行き①ー(西谷)→各停横浜行き<西谷始発>
- 各停JR新宿行き、特急横浜行きー(二俣川)→各停横浜行き②
- 快速横浜行き②ー❌→各停横浜行き(乗継への有効列車にならない)
湘南台方面からは、
- 各停横浜行き①
- 各停横浜行き②
- 各停川越市or和光市行きー❌→各停横浜行き(乗継への有効列車にならない)
このようになるため、西谷〜横浜間の各停のみの停車駅へ行くための有効列車が減少してしまっています。また、有効列車の発着間隔も、従来の10分に1本のペースから、
- 海老名発(特急除く):各停ー(6,7分)→快速①ー(7分)→各停ー(16,17分)→各停…
- 湘南台発:各停①ー(12分)→各停②ー(18分)→各停①…
このようにダイヤホールが生じてしまいました…
様々な列車の兼ね合い、終着駅での折り返し時間の適正化など、理由は考えられますが、これだけ接続がグチャグチャになってしまうと、利用者に対してより混乱を招きかねないことになるでしょう。
③横浜より新横浜優先?二俣川での発着順序逆転。
プレスリリースでもあった通り、湘南台→新横浜間を走る列車(東横線へ直通する各停)の所要時間を3分短縮させることとなりました。従来のダイヤを見ると、長時間停車を行う駅が二俣川での4分停車しかなかったため、所要時間短縮のためには、二俣川での停車時間を減らす、すなわち、二俣川で接続を行う海老名発の快速横浜行きを”待たせて”先に発車することはほぼ確定となり、実際に発表されたダイヤも、快速横浜行きを二俣川で”4分”も待たせた上で各停を優先運行させることとなりました。

但し、JR直通や東急直通、新横浜乗り入れに伴う新幹線とのアクセス構築がなされたものの、相鉄沿線民の1番の目的地は”横浜駅”であることには変わりはありません。その横浜駅に向かう列車(しかも優等種別)を差し置いて、新横浜駅とその先の都心方面へ向かう列車を優先させるべきなのか?という疑問を抱いた方もいるでしょう。
実際に相鉄が算出している1日平均乗降人員[https://cdn.sotetsu.co.jp/media/2024/sustainability/reports/joko2023.pdf]に関しても、
新横浜駅: 38,147人(22年度)→53,414人(23年度)
<※通過人員(東急方面へ直通する人員)含む>
に対して、
横浜駅: 329,228人(22年度)→314,649人(23年度)
となっており、直通開始によって横浜駅を経由して都心方面へ向かっていた利用客の一部が、直通線を経由して都心方面へ向かうルートへシフトした影響もあるとはいえ、それでも横浜駅を利用する方が大半な事実は変わりありません。
このことから、最主要駅の横浜駅へ向かう列車を優先して走らせるべきだろ!と声を挙げる方が現れても不思議ではありません。
事実、新横浜駅での各停の所要時間も従来通り”5分”と長めに停車することに変化がないため、仮に二俣川発車時刻を快速横浜行きの後に設定したとて、新横浜駅での時間調整が短くなることから、東急線方面への影響はないため、尚更思うことでしょう。
ここで、相鉄側がなぜここまで半ば強引に所要時間短縮を優先させたのか理由を考察してみると、1番は“新横浜での東海道新幹線下り(名古屋・新大阪方面)の乗継時間確保”と考えられます。
特に、新横浜を毎時58分に到着する各停だと、約9分の乗継で、新横浜を毎時07分に発車する広島行きの定期のぞみ号に乗り継げることが大きいと思われます。よって、各停の到着時刻を遅らせてしまうと、その分新幹線への乗継が厳しくなってしまうことから、止むなく各停を優先させたと捉えられます。
但し、羽沢横浜国大→新横浜間の20分ダイヤホールを埋める”シャトル列車”さえ、各停の前に運行できれば、無理に各停の所要時間を縮めなくても新横浜駅で余裕を持って新幹線に乗り継ぐことも可能だと思うので、そこはどうにかならないものかと思います。
むしろ、二俣川で待たされる方の快速横浜行きの海老名→横浜間の所要時間は34分から36分に2分延びるので、そっちの影響の方が大きいでしょう。
④いずみ野線上りも10分等間隔ではなくなる。

いずみ野線の湘南台→二俣川間も、従来の10分等間隔から、
06-(12分)-18-(10分)-28-(8分)-36-(12分)-48-(10分)-58-(8分)-…
※湘南台駅発時刻
このように不均等な間隔となってしまいました。06,36分発が他よりも2分早く出発する理由としては、“終点の横浜まで1度も優等列車の待ち合わせを行うことなく逃げ切るため”ですが、他の各停は二俣川で待ち合わせで少々停車するなど役割が大きく異なるため、少し利用しづらくなってしまうでしょう。利用する際は発車時刻に注意が必要です。
⑤沿線はやはり、急行の復活を切に願っている。

そして、毎度毎度改正の度に復活の声が挙がっている急行の復活。2021年の減便ダイヤによる日中パターンダイヤでの運行がなくなり、そして2023年の東急直通開始を機に休止となってしまったかつての大エースは、本改正でも復活は叶いませんでした。
特に二俣川〜瀬谷間の各駅民は勿論、相模大塚〜かしわ台間の各駅民、なんならいずみ野線の各駅民ですら、横浜〜二俣川間ノンストップの急行に未だ強いこだわりを見せています。快速はあまりにも停車しすぎ、特急だと逆に通過しすぎて乗換がめんどくさいというイメージがつきがちな中で、沿線のフラストレーションは引き続き溜まったままと思われます(多分)。加えて今改正で所要時間が延びるのが当たり前になってしまうと尚更のことです。

勿論、西谷を通過することで直通線方面に向かう方が間違って横浜駅まで飛ばされないようにしないことを引き続き懸念しているものと思われますが、直通線もぼちぼち定着しつつあり、尚且つ遠近分離の適正化を再び図るためにも、そろそろ復活していいのではないでしょうか?
まとめ:①〜⑤の不満を全て解決する(?)パターンダイヤはこれだ!
ダイヤ改正直前まで、悪戦苦闘しながらも全ての列車運行をまとめた相鉄のスジ屋さんには大変申し訳ないのですが、正直個人的に今改正のパターンダイヤに良いイメージが持てなかったので、その不満点や課題点を全て解決する(であろう)パターンダイヤを考えましたので、以下に示します。
いかがでしょうか?各課題点や問題点をどのように解決したかを示すと、
- 新横浜〜西谷シャトルを設定して20分以上のダイヤホールを解消
- どの列車でも二俣川or西谷での優等↔︎各停の接続をキッチリと確保
- 新横浜より横浜優先!新横浜到着時刻が遅くなる分は1のシャトル列車でカバー
- いずみ野線10分等間隔運行を維持
- 30分に1本、前後の列車との間隔や乗換回数1回制限を上手く調整すれば急行の運行はほぼ問題ナシ
当然このダイヤも課題があり、
- 横浜・西谷・海老名での折り返し運転に課題
- 新横浜〜西谷シャトル設定に伴う運行コスト増大
- 急行の誤乗問題対策
といった懸念材料は抱えていますが、ここ最近の沿線需要に対する方向性を見直すためにも良いのではないでしょうか?
皆様、特に沿線民の方は今回の改正や改善案に関してどのように思っていますでしょうか?
今回はここまでとなります。最後までご覧いただきありがとうございました!