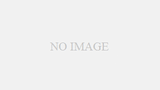皆様、こんにちは。U5swです。
今回は、主に関東で活躍を続けてきた通勤型車両が、最近続々と”九州”に譲渡されていることについて、詳しく見ていきます!
大手鉄道会社→大手鉄道会社への車両譲渡は”西武”のイメージが強いが…
日本の鉄道では、新型車両の導入で追い出された鉄道車両を、そのまま廃車解体することもあれば、他の鉄道会社に譲渡した上で再活用することがあります。
鉄道車両の譲渡と言えば、
- 大手鉄道会社から地方ローカル鉄道会社へ譲渡
- 大手鉄道会社から外国の鉄道会社へ譲渡
これが定番というイメージが付いていました。
しかし、最近になって、
- 大手鉄道会社から別の大手鉄道会社へ譲渡
するケースが目立つようになりました。その代表例が、
“西武鉄道のサステナ車両”
です。小田急電鉄と東急電鉄という、同じ関東の大手私鉄会社の車両を譲り受けて、旧型車両の置き換えを進める動きが活発化しています。
↑西武鉄道サステナ車両の現状はこちらの記事を参照願います。
しかし、今年に入って西武鉄道とはまた別のケースで、
“大手鉄道会社から大手鉄道会社への車両譲渡”
が実現しています。その会社間とは、
“JR東日本“から”JR九州“への車両譲渡
です。果たしてその車両と使用用途とはなんでしょうか…?
今回譲渡が実現した車両と使用用途を深掘り!
まず、この9月にJR東日本→JR九州への譲渡が実現した車両は、
“E501系”
という通勤型車両です。E501系は1995年から1997年にかけて製造された“交直流”通勤型車両であり、10両編成4本と5両編成4本の計60両が製造されました。

↑E501系通勤型電車(Photo ACより引用)
常磐線の輸送改善を目的に製造され、上野〜取手間の直流区間に限らず、取手以北の交流区間も走行できるよう、日本で初めての交直流両用の4ドア通勤型車両として開発がなされました。
設計は当時京浜東北線(現在は房総地区)の主力車両だった209系をベースとしており、外観はまさに”209系の交直流電車ver.”と言えます。
登場当初から2007年改正までは、主に常磐線の上野口(上野〜土浦間)での運用に就いていましたが、2005年に登場したグリーン車付きの後継交直流通勤型車両・E531系が登場したことにより、2007年改正以降は上野口の運用から撤退し、主に常磐線の土浦〜いわき・草野間と、水戸線(付属編成のみ)の運用となりました。
但し、水戸線の小山〜小田林間のデッドセクションで交直切替の故障が頻発したことや、常磐線・水戸線のワンマン運転拡大により、E501系の運用がどんどんE531系に置き換わっていったことで、JR東日本からすると、故障が相次ぎワンマン運転に対応していないE501系は、お荷物と化してしまいました。
そして遂に、2024年3月のダイヤ改正では、5両編成(付属編成)の運用が完全に消滅してしまったことで、4編成の内1編成(K751編成)は惜しまれつつ廃車解体がなされました。また、1編成(K754編成)は2023年にイベント列車“E501 SAKIGAKE”として改造がなされ、常磐線や水戸線で臨時列車として運行がなされています。
では、残りの2編成(K752編成、K753編成)は何処へ…?
そう、この2編成が今回”JR九州への譲渡車両“となったのです。
なお、5両編成の内サハ車両1両を抜いた “4両編成”を組成し、抜いたサハ車両を除き外装の帯は全て剥ぎ取られた“無塗装状態”で、2編成を連結した8両編成の前に牽引機関車を連結し、2025年9月9日に郡山車両センターを出発、1000km以上の長旅を経て、同年9月12日に九州へ上陸しました。
では、なぜ今回E501系の九州譲渡が実現したのでしょうか? キーワードは以下の2つであり、
“交直流車両”と”関門海峡”です。
先述の通り、E501系は直流電化区間の上野口と交流電化区間の取手以北の両方を走行できるよう、“交直両方に対応したハイテクな車両”となっています。
全国の鉄道で直流区間や交流区間が混在しているため、両区間を走行する区間にはこの交直流車両が用いられてきましたが、ハイテクで便利な分、その車両を製造するコストに関しては、直流専用車両や交流専用車両と比較すると、どうしても高くついてしまいます。その製造コストを懸念し、加えて乗客の輸送密度が小さい交直流区間においては、電化しているのにも関わらず、電化方式に全く依存しないディーゼル気動車を導入しているところも存在します(例:えちごトキめき鉄道日本海ひすいラインを走行する普通列車、JR東日本羽越本線村上〜間島間を走行する普通列車)。
そんな中でJR九州の電化区間は大多数が交流区間であり、直流区間は福岡市営地下鉄空港線と相互直通運転を行なっている筑肥・唐津線(姪浜〜西唐津間)と、山陽本線の“関門海峡区間(下関〜門司間)”であり、その中でも下関〜門司間に関しては交直を切り替える”デッドセクション”が存在します。
これまでこの関門海峡区間には、“国鉄型車両の415系”が暫く使用されていますが、老朽化が進行して置き換えが迫っている状況です。
↑JR九州の415系(鋼製車、既に引退済み)

↑JR九州の415系(ステンレス車)
しかし、JR九州は国鉄分割民営化後、JR九州オリジナルの交直流車両を製造したことがなく、加えて関門海峡区間しか交直流車両を必要としないため、新たに高価な交直流車両を開発・製造するのはコスパが悪すぎます。
かといって、最新のハイブリッド気動車(例:YC1系)や蓄電池車両(例:BEC819系)で置き換えるのもそれはそれで違う…
そこで白羽の矢が立ったのが、JR東日本で余り物と化していた、E501系だったのです!
登場から長くて30年が経過した当形式、近年デッドセクション区間で故障が頻発していた等、多少懸念はありますが、今後問題なく整備されると思いますし、交流の周波数が異なる問題(関東:50Hz、九州:60Hz)に関しては、50Hz地域→60Hz地域で使う分には変圧器に何ら問題ないとのことです(逆に、60Hz地域→50Hz地域で使うことは不可)。
↑異なる周波数に対する変圧器問題に関する参考文献(ダイヘン様)
当然、交直流機器以外にも保安装置の改修やE501系からの改番等が必要ですが、どのような姿となって我々の前に現れるのか、楽しみに待ちましょう。
JR東日本→JR九州への譲渡は以前にも実現していた
今回のE501系のJR東日本からJR九州の譲渡に関しては、世間的に見ると“異例”というイメージがつくと思いますが、実は17年前の2008年に、E501系と同様の事例で415系の一部車両がJR東日本からJR九州に譲渡されたことをご存知でしょうか?
E531系の導入完了によって常磐線での運用を終えた415系の内、113系・115系ベースの鋼製車500・600番台、4両編成2本と、211・213系ベースのステンレス車1500番台、4両編成1本が、JR九州へ譲渡されました。
今回のE501系譲渡が実現した要因として、過去に415系をJR九州へ譲渡したというルーツがあったからというのが大きいでしょうね。
譲渡されたのはE501系だけではない!? JR線でも大活躍したあの車両も!
そして、E501系の少し前に、同じ関東で活躍していた車両も、同様にJR九州に譲渡されていました。それが、
東京臨海高速鉄道70-000形
です。新木場〜大崎間を走る第3セクター鉄道、東京臨海高速鉄道りんかい線で1995年開業時から活躍を続けている70-000形。JR209系をベースとしており、自社のりんかい線に加えてJR埼京・川越線にも乗り入れ、”ほぼJR東日本”の車両としても活躍を続けてきました。

↑東京臨海高速鉄道70-000形
そんな70-000形も一部車両は製造から30年が経過し、JR東日本ではE233系やE235系といった最新技術を取り入れた新型車両が主力となっている一方で、りんかい線は未だ209系ベースの1,2世代前の車両を走り続けてきたことから、今の時代のニーズにあった車両へ更新すべく、新型車両71-000系の導入が決まり、70-000系は順次役目を終えることとなりました。
置き換えられる70-000形の今後の行方として、単純に廃車解体されるか、ベースとなった209系が譲渡された伊豆急行への譲渡、サステナ車両として西武鉄道へ譲渡など色々な予想を立てていましたが、今年の6月、私含めほとんどの方がびっくりしたであろう、衝撃の譲渡先が明らかとなりました。それが、
JR九州
でした。これを聞いた時、あまりにも衝撃すぎて開いた口が塞がりませんでした…
譲渡の目的と置き換える車両について深掘り。
今回の70-000形譲渡に至った理由はすなわち、
筑肥線の103系を置き換えるため
です。

↑筑肥線末端部で活躍する103系。かつては6両編成を組み筑前前原〜福岡空港間も走行していたが、305系の導入で3両編成かつ末端部のみの運転に留まる(Photo ACより引用)
国鉄の通勤型車両として様々な場所で活躍した103系。現在は風前の灯となり、2025年現在103系が残存する路線は、
- <JR西日本>加古川線(加古川〜谷川間)
- <JR西日本>播但線(姫路〜寺前間)
- <JR九州>筑肥・唐津線(筑前前原〜西唐津間)
のみとなっています。
今回、筑肥線の末端部(筑前前原以西)のみで細々と活躍を続ける103系が、老朽化等を理由に置き換えを行わなければならず、その置き換え用として抜擢されたのが70-000形となったわけです。
事実、JR九州は、唯一の全線直流電化区間である筑肥線、および福岡市営地下鉄空港線乗り入れ用車両として、4ドア6両固定編成の303系を1999年に、305系を2015年にそれぞれ登場させています。

↑JR九州の303系電車。

↑JR九州の305系電車。
特に305系に関しては、登場から10年しか経っていないことから、
末端部用の305系を新たに増備すればいいのでは?
と思った方もいるでしょう。但し、車両新造には当然コストがかかりますし、それよりも丁度70-000形が運用を離脱するので、譲渡してもらう方が色々と都合がよかったのでしょう。好都合なタイミングが功を奏した、今回の譲渡となりました。
2両に減車?クハ→クモハ化で大規模な改造へ?
今回の70-000形の譲渡は既に始まっています。2025年5月にZ8編成が運用を離脱しており、中間車は全て廃車解体のために輸送されましたが、先頭車の2両(70-080号車と70-089号車)に関しては、東京港へ輸送され、なんと“海上輸送”にて九州へ旅立ちました。
そして新門司港まで船で運ばれた後、再度トレーラーにてJR九州の小倉工場へ到着。筑肥線末端部用に向けての改造が行われているようです。
ここで気になる点として2つ挙げられるのが、
- 中間車1両含めた3両ではなく先頭車のみの2両で運ばれたこと
- 先頭車は両方ともモーターのないクハ車であること
ということです。
まず、現在筑肥線の末端部用で活躍している103系は3両編成を組んでいて、その103系を置き換えるためなら“3両編成”で置き換えるものと思われましたが、実際小倉工場まで運ばれた70-000形は先頭車のみの“2両”です。
こうなると、3両編成を2両編成で置き換えることとなり、輸送力が落ちてしまうこととなりますが、筑肥線の末端部という輸送量の少ない区間ということもあり、2両編成でも事足りるという判断なのでしょうか?
一応、筑肥線末端部に関しては6両編成の303系や305系も運用に入っているため、利用者の多い時間帯に関しては6両編成を入れれば混雑対策にもなるでしょう。
次に、70-000形のモーター車に関してですが、先頭車はどちらもモーターはついていなく、中間車8両の内6両に搭載して10両編成を組んでいるため、今回新たに2両編成を組成する場合は、どちらか1両を電装化(クハ→クモハ化)しないといけない大掛かりな工事を行う必要があります。
中間車についていた従来のIGBT-VVVFインバータを供出して取り付けるのか、はたまたJR九州側で新たな電装装置を取り付けるのか、こちらも気になるところです。
まとめ: 色々びっくりな九州譲渡の2形式
いかがでしたでしょうか?
今回は関東で活躍していた通勤型車両2形式が、JR九州へ譲渡される話題を紹介しました。
E501系も70-000形も製造から30年が経過し、車両の世代交代スパンの早い関東の鉄道会社では世代が古い車両として置き換えられることとなりましたが、JR九州の場合は、それ以上に長く活躍する老兵達がヒィヒィ言いながらも今日まで活躍を続けており、お互いの車両交換タイミングの思惑が一致したことで、今回の譲渡が実現しました。
今後この2形式がどのような姿となって、JR九州の一員として活躍するのかがとても楽しみですね!
今回はここまでとなります。最後までご覧いただきありがとうございました!